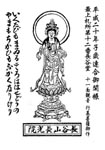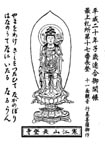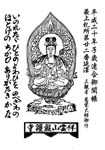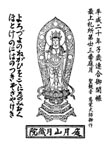それがきっかけで、観音様に本曲を聴いて頂く喜びに目覚めて「虚無僧」となった。
先達に導かれた巡礼の経験が無いので所作は我流である、四国遍路で覚えた所作(合掌禮拝・懺悔文・三帰・三竟・十善戒・発菩提真言・三昧耶戒真言・開経偈・般若心経か観音経を読経)の間に息を整えて、本曲を献曲する、その後 十三佛真言・光明真言・ご本尊真言・舎利禮文と一通り行うと、本曲にもよるが大体25分〜35分位のお勤め時間となる。
今年(子年)は最上三十三観音御開帳と聞き、私の普化尺八の原点である最上三十三観音の巡錫を思い立った。
6月10日に発願して天童駅から歩き出し、主として仙台から日帰りで通って9月18日に真室川駅まで到着して結願となった、実巡礼日数は10日間の歩き遍路であった。
(連合御開帳期間は5月1日より10月31日まで)
| 2008年6月10日(月) | |||||||||||
| 仙台〜天童駅〜1 若松〜2 山寺〜番外 山寺奥の院〜山寺駅〜仙台 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 2008年6月12日(水) | |||||||||||||||||||||||||
| 仙台〜山寺駅〜2 山寺〜3 千手堂〜4 圓應寺〜5 唐松〜山交BT〜仙台 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2008年6月24日(火) | |||||||||||||||||||||||||
| 仙台〜山寺風雅の里〜7 岩波〜9 松尾山〜10 上の山〜11 高松〜高松BT〜仙台 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2008年6月27日(金) | |||||||||||||||||||||||||
| 仙台〜山交BT〜8 六椹〜7 岩波〜6 平清水〜5 唐松〜山交BT〜仙台 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
7月・8月の暑い時期を避けて遍路再開は9月に入ってからとした
7月はヨーロッパアルプスのスイス・フランス各地で献曲をした、特にアイガーバント駅ではヨーロッパで亡くなった岳友の為にアイガー北壁を見下ろしながら「回向」献曲、音を抑えたつもりだったがトンネルの中は思いの他音が響き渡ったようで外人観光客が大分よってきた、また教会での献曲(「手向け」「息観」が多かった)の時は、いずれの教会も音響効果の良さに驚いた。
8月は恒例の上高地、11日滞在した間は毎朝穂高に向かい「手向け」「回向」を献曲した。
また、縦走や登山も数度行ったがピークでは献曲出来ず、宿泊地で朝と途中に有る神社仏閣で献曲した。
| 2008年9月2日(火) | |||||||||||||||||||||||||
| 仙台〜高松BT〜11 高松〜12 長谷堂〜13 三河村〜14 岡村〜羽前長崎駅〜仙台 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2008年9月4日(木) | |||||||||||||||||||||||||
| 仙台〜西川B停〜西川町〜17 長登〜15 落裳〜16 長岡〜18 岩木〜東根駅〜仙台 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2008年9月15日(月) | |||||||||||||||||||||||||
| 仙台〜東根駅〜19 黒鳥〜20 小松沢〜21 五十沢〜22 延沢〜23 六沢〜24 上の畑〜尾花沢「Hおもたか」 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2008年9月16日(火) | |||||||||||||||||||||||||
| 尾花沢〜30 丹生村〜28 塩の沢〜29 大石田〜27 深堀〜26 川前〜25 尾花沢〜尾花沢「Hおもたか」 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2008年9月17日(水) | |||||||||||||||||||||||||
| 尾花沢〜31 富沢〜番外 世照〜32 太郎田〜瀬見温泉「喜至楼」 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2008年9月18日(木) | |||||||||||||||||||||||||
| 瀬見温泉〜33 庭月〜真室川〜山形〜仙台 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||